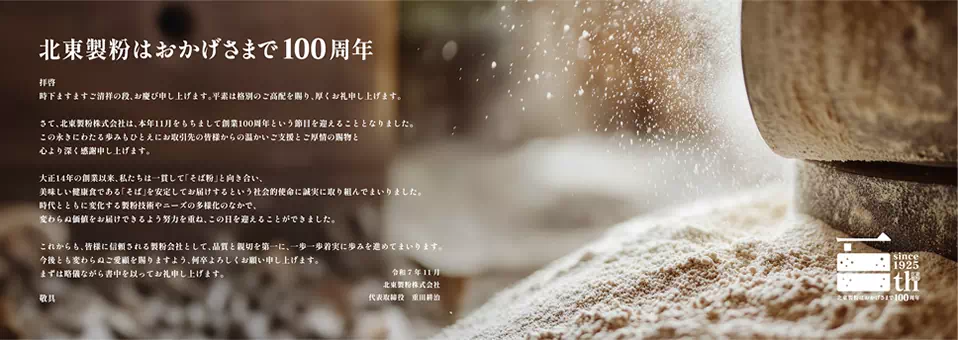

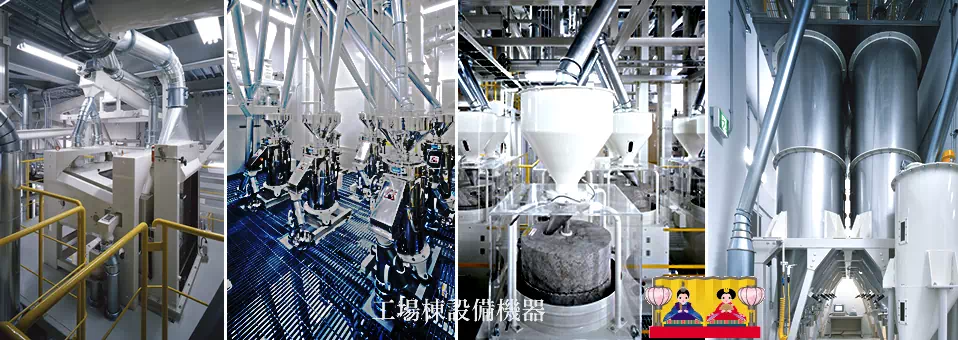
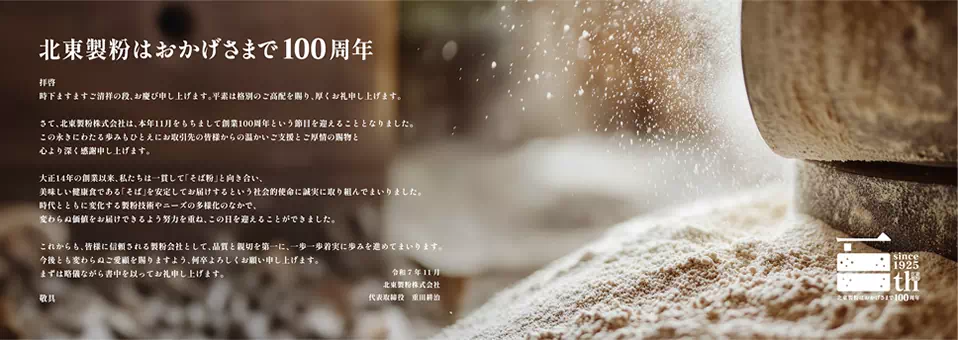

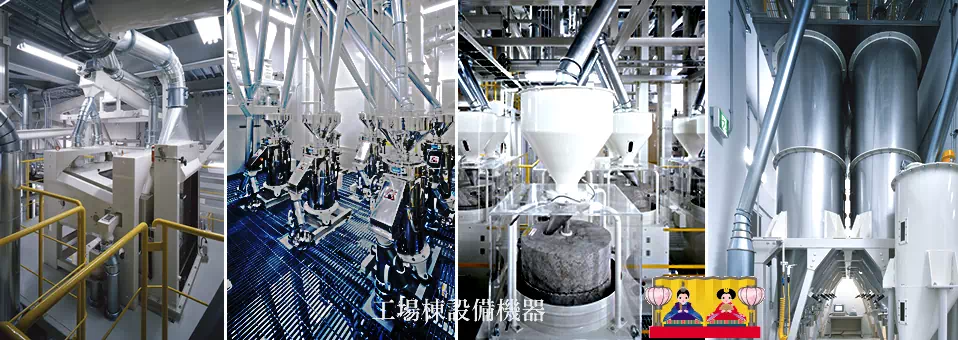
元禄時代(1688~1704)以降江戸では麺棒を三本使って打つ「江戸流」の技術が創案されました
江戸の蕎麦打ち技術が他の地方に比べて格段に向上発展したのはこの独特の技術によるところが大きいです
麺棒を三本使う理由を簡単に言えば麺帯を出来るだけ長く大きくかつ均等な幅均一な厚さに平らに延ばす為です
これによりそばに切った時に無駄な部分が出ず均一な長さのきれいなおそばができます
「江戸流」で使用されるの三本の麺棒は巻き棒(長さ120㎝)が二本と打ち棒(長さ90㎝)が一本で太さはそれぞれ直径3㎝が普通です
材質は檜が最も適しているとされていますが樫や朴の木も用いられています
麺棒は細い方が麺帯と生地の密度が高くなり表面が荒れません
つまり肌が滑らかでしっかりした粘着力のある麺帯に仕上げる事ができます
麺棒は細いばかりでなく同時にある程度の柔軟さと軽さとを備えた材質である事が要求されます