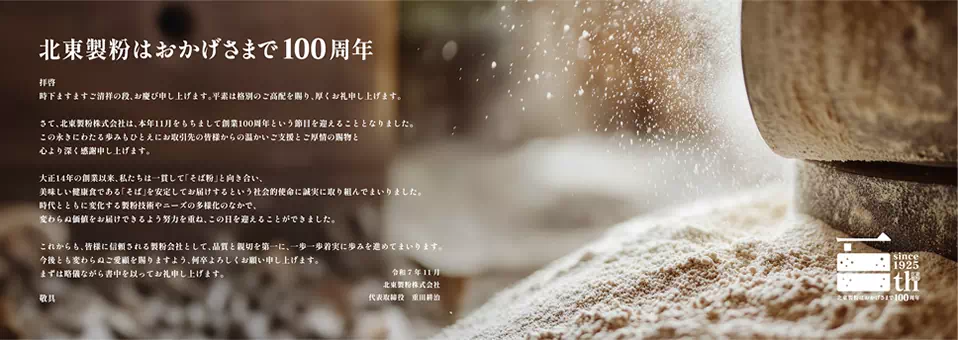

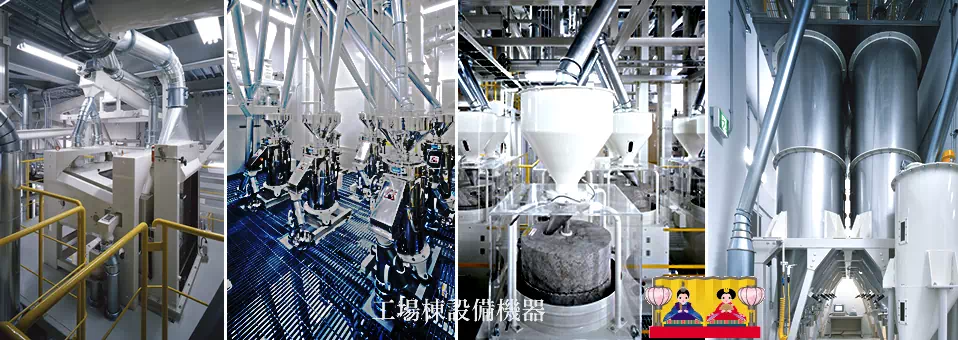
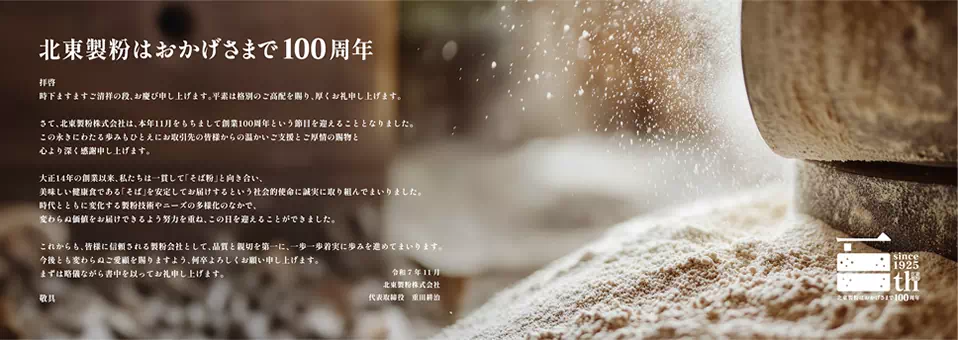

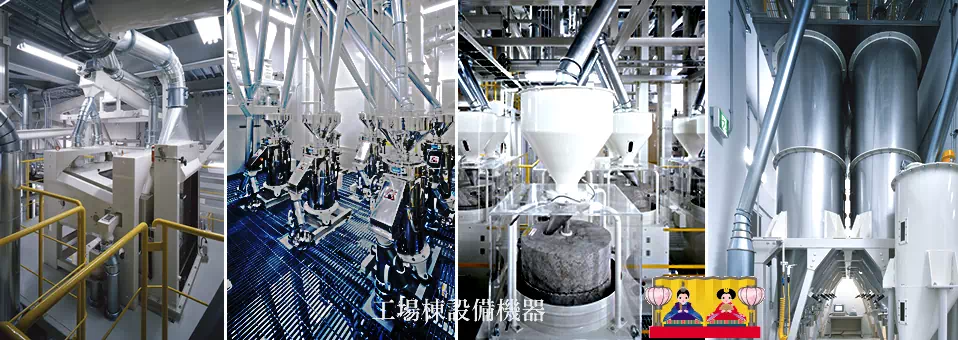

上石と下石には幾何学模様な目が刻まれています
下臼の上に上臼を裏返しにして重ね合わせると上下の臼の目が重なり上臼を反時計周りに回せばそれぞれの目の交点が外周方向へ移動します
その為上下臼の間にある粉砕物は外周方向へ送り出されます
臼の目は送り機構を構成しているのでもし時計方向に回しても粉砕物は臼の外側には出てきません
一見単純で原始的な形をしていますが基本的に石臼は精密機械の機能を備えています
だから石臼で挽けばなんでも美味しいというわけではありません
臼の調整が精密機械並みに行われているかどうかが問題です
石臼の石材・形態には地方色があります
石はそれぞれの地方で入手しやすく臼にしやすく臼に向く石が選ばれています
それはその地方でもっともありふれた石のことが多いです
上臼と下臼の目(模様)ですが近畿・中部圏では八分画が多いのに対して関東・東北では六分画が主になっています
上臼の回転方向は反時計方向が圧倒的に多いです
しかし佐渡地方だけは時計方向回しです