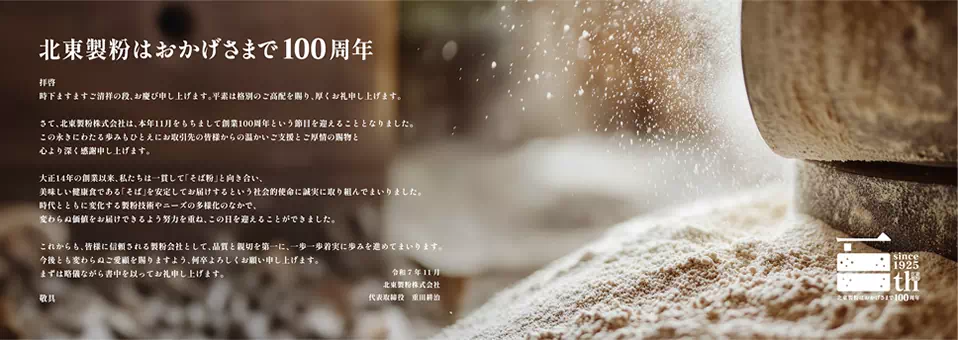

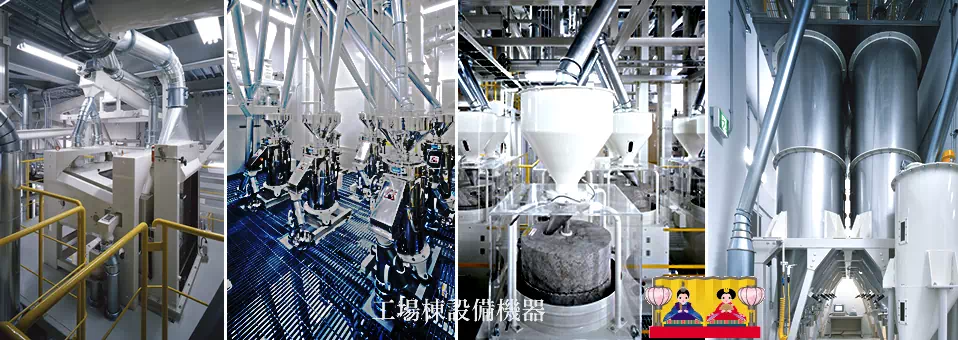
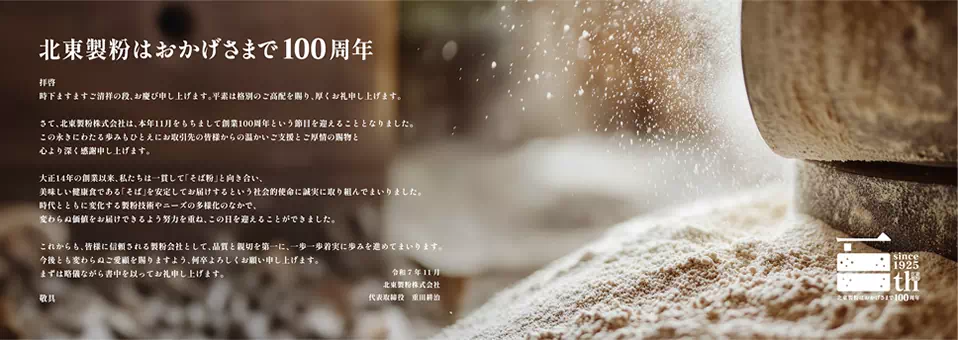

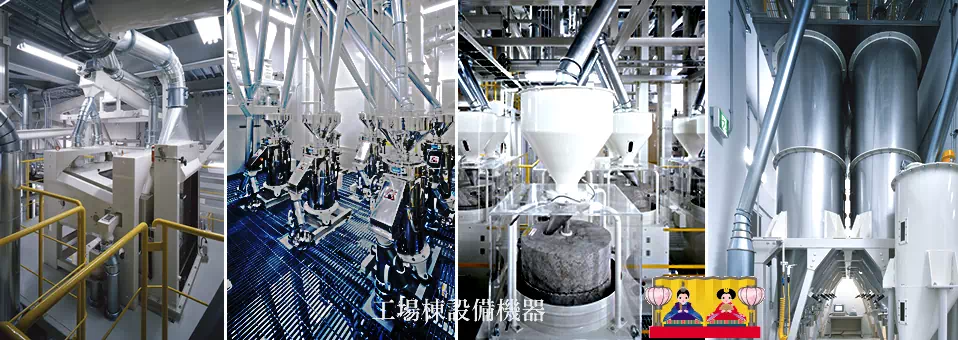
生蕎麦の本来の意味はつなぎを加えずそば粉だけで打ったそば(生粉打ち「きこうち」)の事で「きそば」と読みます
江戸前期においてそばはすべて「きそば」であり小麦粉をつなぎに用いるようになったのは江戸時代中期以降の事です
最初は麺のつながりを良くする為に加えていた小麦粉の量が次第に増えいわゆる二八そばが一杯十六文を表示した寛延・宝暦(1748年~1764年)はまだしもそばの品質は低下の一途をたどり二八そばはついに駄そばつまり粗雑なそばの代名詞になり下がってしまいました
一方高級店は座敷を設け「手打ち」あるいは「生蕎麦」を看板として二八そばとのグレードの違いを強調していました
もちろん製麺機の無い時代の事でどちらも手打ちにかわりないが精製という意味であえて「手打ち」といった事です
しかし幕末頃になると二八そばまでが「手打」や「御膳生蕎麦」を名乗るようになり判別がつかなくなってしまいました
現在暖簾や看板に「生蕎麦」や「御膳」と書いたりするのは当時の名残で一般には生粉打ちを意味する事はありません
ところが昭和50年代に入ったあたりからもう一つの「生そば」という表示が登場しました
テイクアウトで家に持ち帰って食べる事のできる生(なま)のそばの事で茹でるだけで良いものになっています