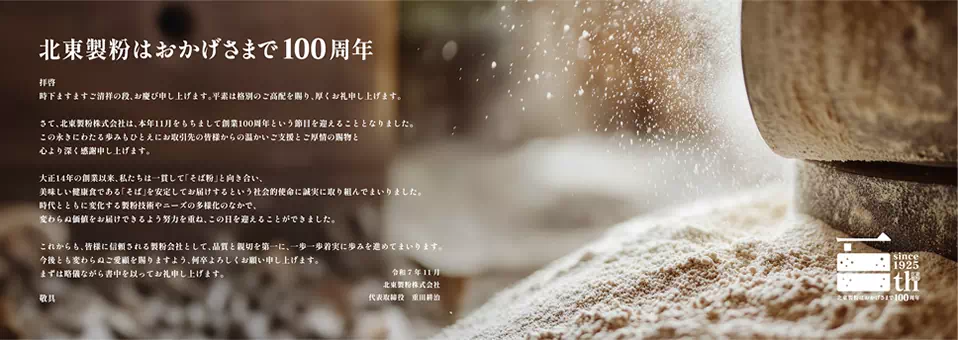

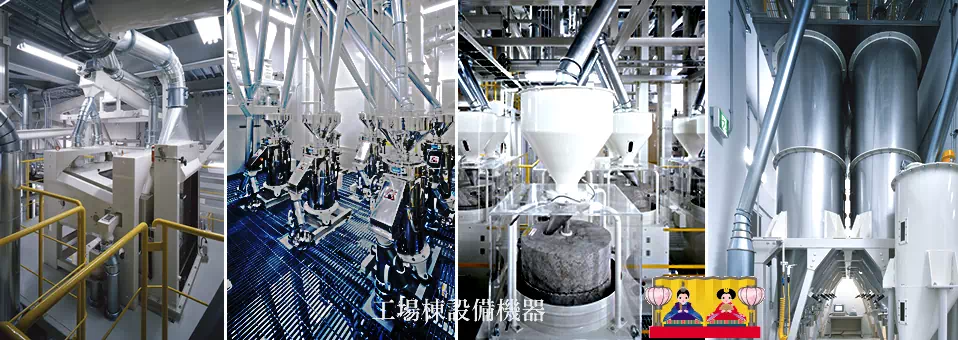
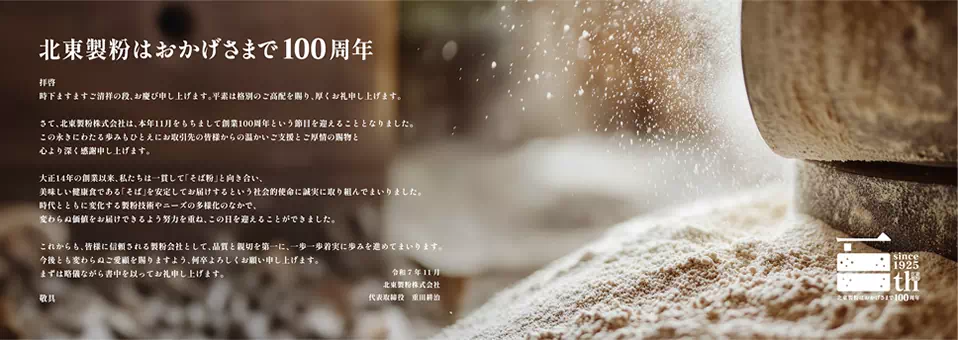

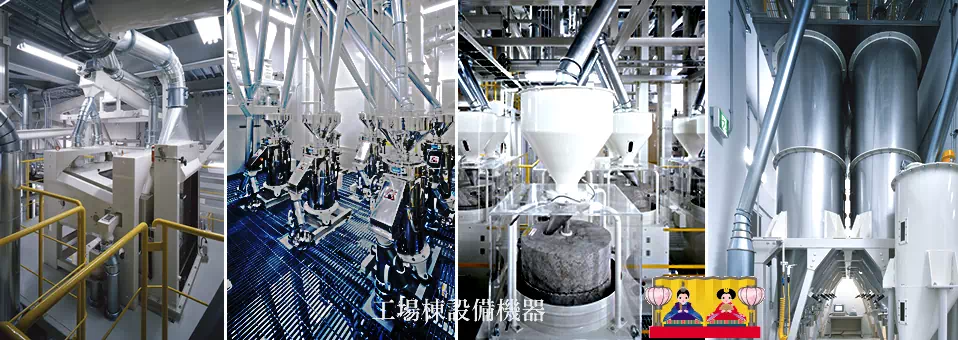
麺類に関する諺で「うどん一尺そば八寸」というのがある
一尺は約30cm 八寸は約24cm
手打の場合のうどん・そばそれぞれの長さの標準を示した言葉で この程度の長さが最も食べやすいからともいわれる
単純に食べやすいという理由だけから わざわざこの長さが標準になったと考えにくい
食べやすさもさることながら それ以前の問題として作りやすさがあったと考えられる
実際そばの場合は麺棒の長さが一つの根拠になっている
通常「江戸流」で使用される三本の麺棒のうち二本の巻き棒の長さは四尺(約120㎝)だ
このまき棒の長さいっぱいの幅に延ばした生地を四つ折りにすると 畳まれた生地の縦方向(包丁が当たる方向)の長さは約八~九寸になる
 もちろんもっと長い麺棒を使えば長いそばができるとも考えられるし信州などではかなり長い麺棒で大きく延ばす打ち方もあるが 刃先のやたら長い包丁を使うのは大変である
もちろんもっと長い麺棒を使えば長いそばができるとも考えられるし信州などではかなり長い麺棒で大きく延ばす打ち方もあるが 刃先のやたら長い包丁を使うのは大変である
江戸流のそば切り包丁の刃の長さは約33㎝が標準でこのくらいの大きさの包丁が最も使いやすいといえよう
ちなみの畳み方には二通りあって生地を向こう側に折っていく「外折り」にすると折り目が折り目が手前になり包丁の刃先が当たらない為倍の長さにしやすいと言われるが 長く出来るかはそば粉の状態や木鉢の技術つなぎの有無や割合などにも影響されるから 一概にはいえないだろう