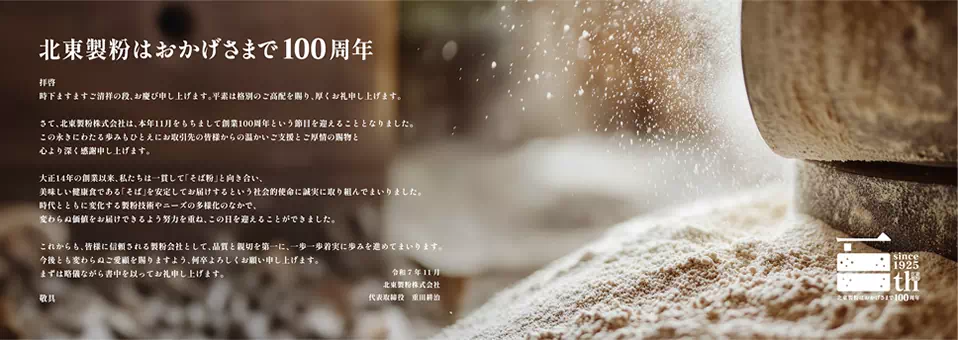

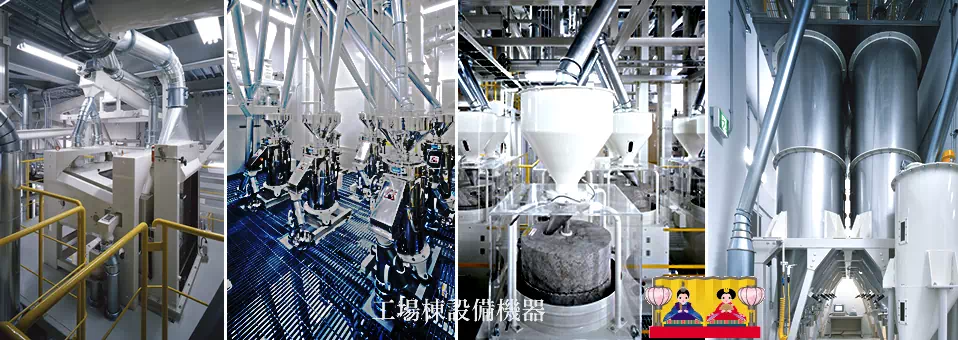
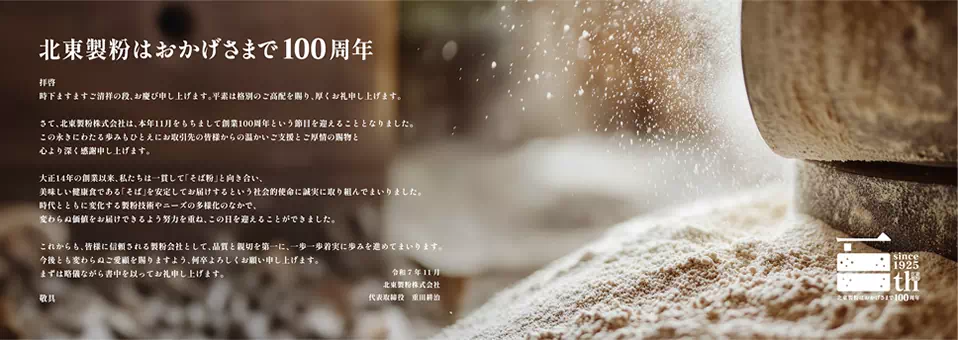

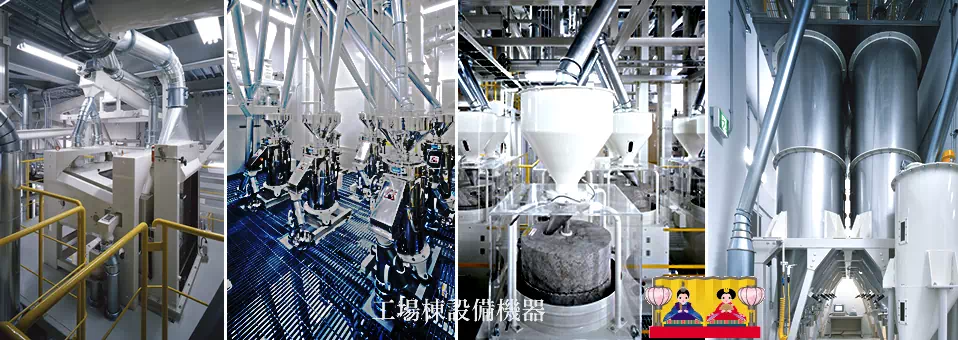
「せいろ」は「蒸籠」のことで 元来は釜の上にはめて饅頭や団子こわ飯などを蒸す為の器であるが 江戸時代初期そば切りを湯通ししないでこの蒸籠でむしてから供する「蒸しそば切り」が流行った
当時はまだつなぎの小麦粉の入らない生粉打ちであったため 茹でると切れやすかった
そこで考案されたのではないかという説や 室町時代から行われていた甑で蒸す蒸麦にならったとする説や うどんは菓子屋で作っていたので蒸すという製法が編み出されたという説もある
幕末頃の品書きを見ると 「もり」ではなく「蒸籠」の名があるから 食器による名目そばであることは間違いない
また天保年間(1830~1844)そば屋が団結して値上げを願い出たが 二八(十六文)を昔からの通り値段だから値上げは許可できないかわりに 蒸籠を上げ底にする事という裁定で今日のあげ簀になった
この時 実際にはそばの量目が減少したものの 見た目には山盛り姿の「蒸籠」のことを新たに「盛り蒸籠」と呼んだ
その呼称がつまって「せいろ」という呼び方が生まれた とも言われている