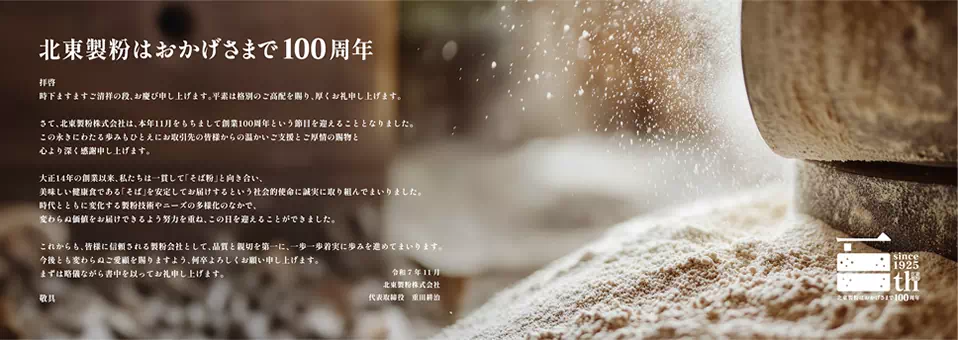

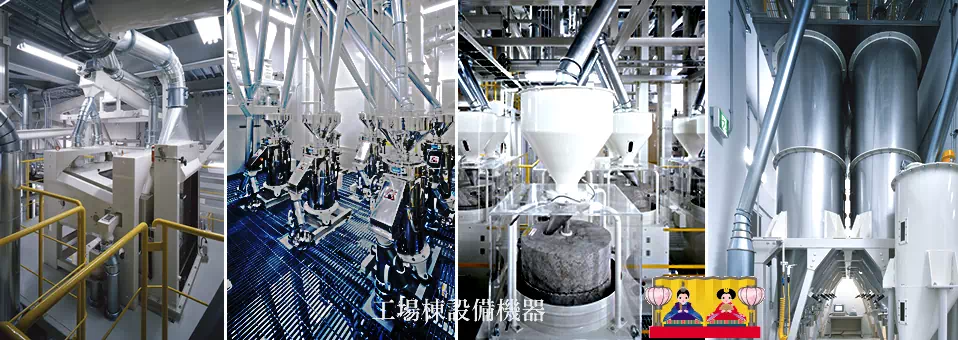
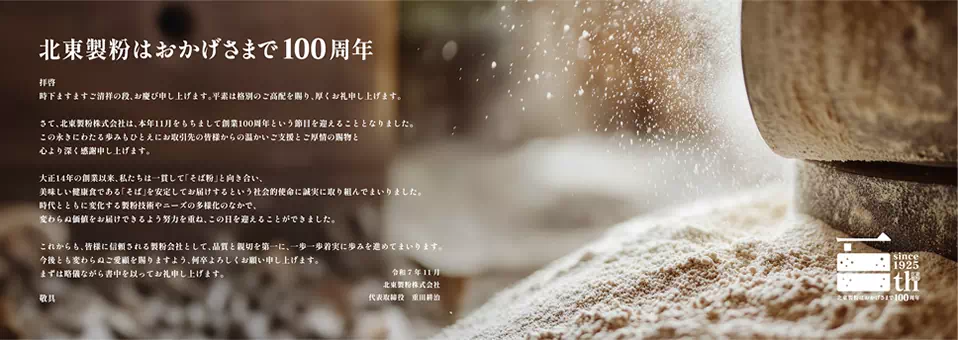

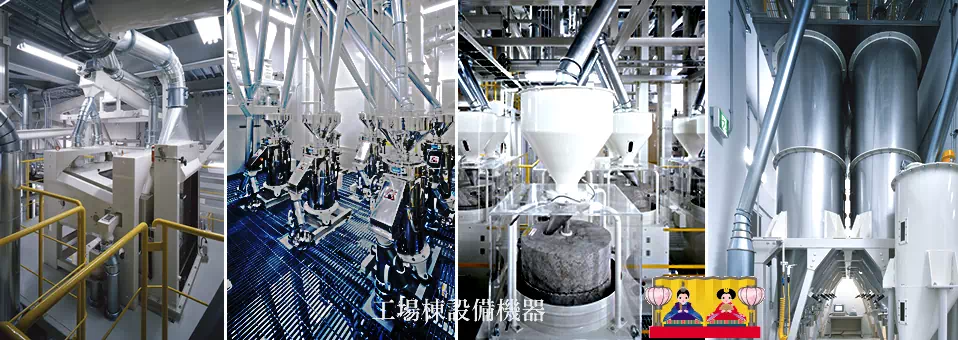
もともとそば切りは汁につけて食べるのが始まりで 江戸時代初期のそば店には現在の「もりそば」一種類しかありませんでした
この食べ方をもっと手軽にしたのが「冷やかけ」です
冬の寒い季節に温かい汁をかけて「ぶっかけ」と称して供していました
この「ぶっかけ」が「かけ」として省略して呼ばれるようになるのは寛政頃からの事になりますが 「もり」と「かけ」は品書きの源流ともいえます
この「ぶっかけ」にいろいろな具をのせたものが加薬そば つまり種もので そばの品書きの基本はほぼ江戸時代に確立していました
その品書きの中で現在ほとんどみられなくなったのが「しっぽく」です
江戸時代の開港場・長崎には中国から伝来した総菜料理が 日本風にアレンジされた卓袱(しっぽく)料理がありました
卓袱料理の中に大盤に盛ったうどんの上にさまざまな具をのせたものがあり これを江戸のそば屋が真似て大平碗に盛り「しっぽくそば」と称して売り出していました
幕末に「おかめ」が出現すると人気が取って替わられ次第に衰退してしまいました